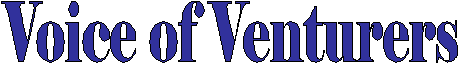
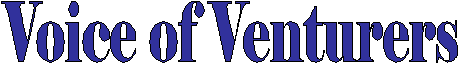
|
樽味 真由子 (1997年・チリ)
初めの3週間はコミュニティープロジェクト。『緑の湖』という名の小さな村で行われた。仕事は湖岸の流木の撤去からいずれはバーベキュー施設の設置。加えて村のオンボロ体育館の修復。降り止まぬ雨、雨、雨、作業自体の村にとっての必要性への疑問、メンバー同士の意見の食い違い。ただでさえ素がでる野外生活。言葉や習慣の違いにさらに驚くことばかり。大きく美しい自然に囲まれながらも、密度の濃い合宿生活はひとりひとりのストレスも伝染しやすい。みんな肩に力が入っていた。今までよりずっとたくましく成長するためにやって来たんだ!というオーラ同士がぶつかり合い、意気込みが空回りしているようだった。 そんな私達のフラストレーションを救ってくれたのが地元の人々の朗らかさ。ウエルカムパーティー、村あげてのゴミひろい作戦、小学校での英語とスペイン語交換授業。キャンプサイトの小川では雪山を見上げながら子供たちと水浴びに歓声(悲鳴!)をあげた。言葉はいらない、ボールひとつと広い原っぱ、それにみんながいる。日本からは1万キロ以上離れた地球の真裏の国。その中の小さな村で見つけたのは特別なものではなく、たくさんの類似した暮らしだった。食べて、働いて、眠る。写真で見たことしかない自分の子供の頃にそっくりな笑顔があった。朝、食卓に並ぶ卵を産むニワトリはゆうゆうと犬の鼻先を横切って散歩している。長く凍える冬があるから、春先に花をほころばせるアーモンドの木々は暖かい太陽の下でいっそう眩しく輝いている。 『La Playa〜!!(スペイン語で「ビーチ」の意味)』。トイレ休憩のサイン。みんな一斉に岸へ向かってパドリングを始める。特に上下つなぎの服を脱ぐ手間のある女の子は一刻を争う。ことさら岸が遠くに見える時だ。アドベンチャープログラムは全行程230kmのシーカヤックによる島めぐり。途中、フィヨルドの島の漁村を訪ねる。地形的に孤立し不便な生活を強いられているその集落で今後のローリーが出来ることは多くあるはずだ。二人乗りのカヤックには16日間の食料とテント、個人装備全てが積んである。パタゴニア名物の強風は残念ながらほとんどが向い風。呪文のように口ずさむ覚えている限りの流行歌も瞬く間に波立つ濃紺の海へと吸い込まれてしまう。一体、私たち進んでるの?座席の水よけカバーもむなしく、手首をつたって入り込んだ水に下着まですでにぐっしょり。今日も後ろを向いて焚き火の火でおしりを乾かしながらのミーティングだ…とほ。
ラグナ・サンラファエル氷河に近付いていることはすぐに分かった。風が変わったから。吸い込んだ空気が鼻孔で冷たい。甲板には色とりどりのレインジャケット、エンジンの低く細かい振動、ガソリンの臭いが漂う難民船!?こうして2日間の船旅の末、環境プロジェクトを行うサンラファエル氷河国立公園に到着。ここでは3週間、保護指定されている野生のネコの調査、公園内の遊歩道の補習を行う。『ホテル・パタゴニア』と命名されたキャンプサイトからは流氷の浮かぶ海まですぐ。ラファエル氷河はパタゴニア最高峰サン・バレンティン山を源に約760平方kmの面積を持つ凍てついた氷の川。海に面した幅3km、高さ60〜80mの先端部は1時間に数回、遠雷のような音をたてて氷河の塊が崩落する。澄んだ空気に距離感を失い、氷塊の余りの大きさにその水しぶきと雪煙はスローモーションのよう。氷河を見下ろす見晴し台で寝袋だけで過ごした一夜、瞼に残像としてはりつく無数の星々と氷河の断続的な崩落音になかなか寝付けなかった。対照的に姿の見えない猫をアンテナの音を頼りに深い森の中に一歩足を踏み込むと、そこは別世界。膝まで埋まるドロに長靴ごと脚をとられる。ひしめく巨木の間の大地は厚い苔がびっしりと横たわり、恐る恐る体重をあずけるとトランポリンのようにフカフカと揺れる。薄暗く湿潤な樹林のなかにいる自分が何やら小さな虫にでもなったような気分。
空と海の境が見分けられないほどどんよりと霧がたちこめている。無数の流氷をよけながらモーターボートの舵をとる時、五感の全てが試されている。誰かが人の一生の鼓動の回数は決まっているらしい、だからドキドキすればする程…と笑った。 ローリーのプログラム後、止まらなくなったように南米の国々を旅し始めた。そこにも様々なドキドキする出会いがあった。きっとその旅の原動力はあの寒さと美しさに震えながら仲間と過ごした日々なのだと思う。いつも「次は何をしようか」と自然に好奇心と可能性を感じられるということ。それは私の体の中に、(遺伝子細胞レベル?で)根をはやした。だから何かに悩んだりつまづきそうになれば、「頭で考えるな」と私の背を押すのはきっとあの時間だろう。最後にこのプログラムと旅にすっかり夢中になった私を様々な折にふれ励まし、なだめ、一緒にドキドキしてくれた家族、友達、アーストレックの皆さんにMuchisima Gracias! |